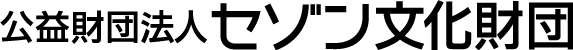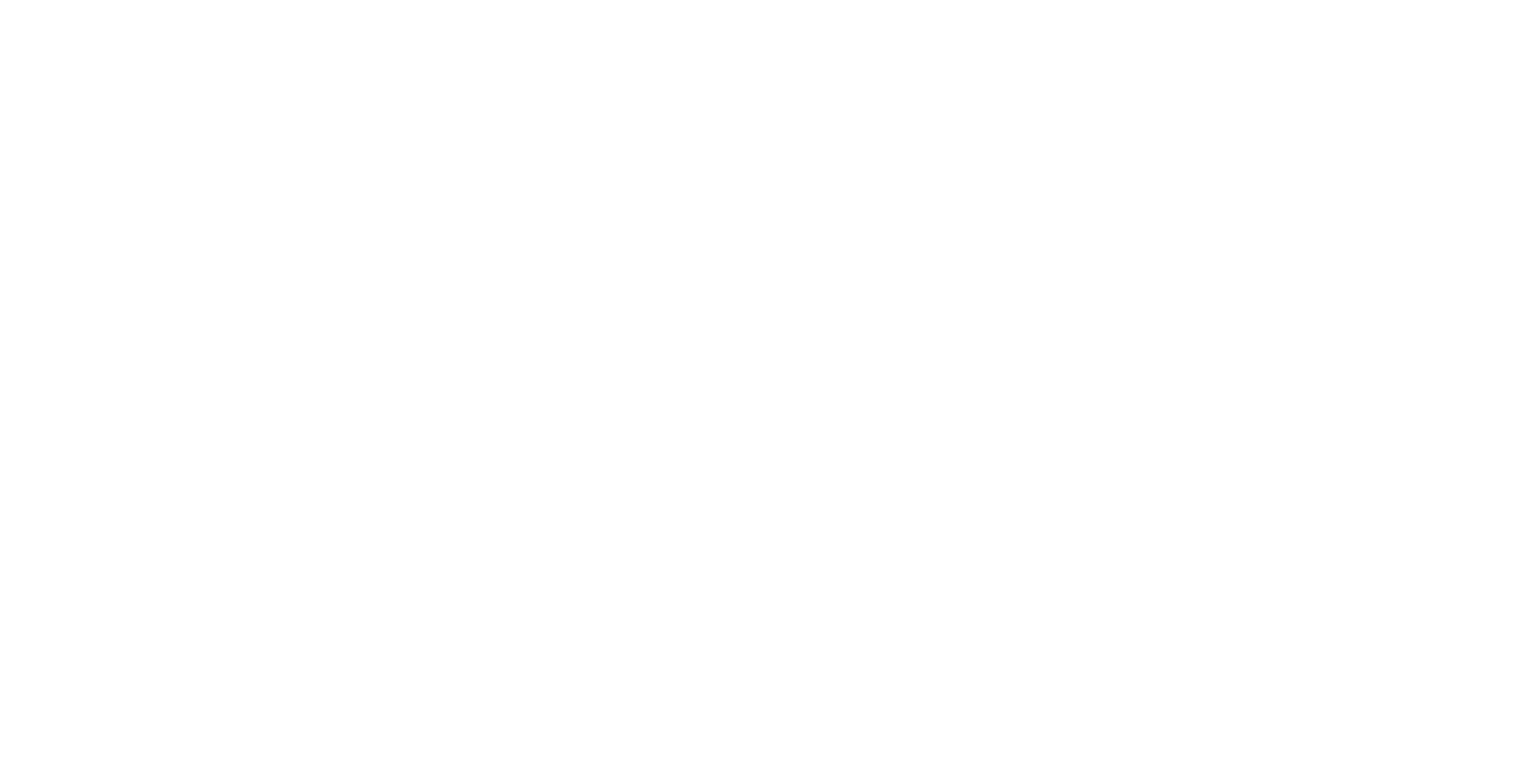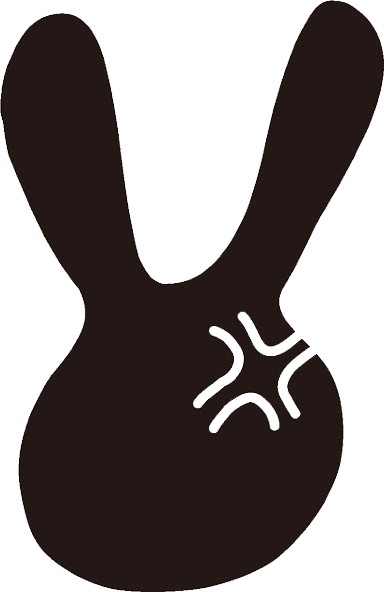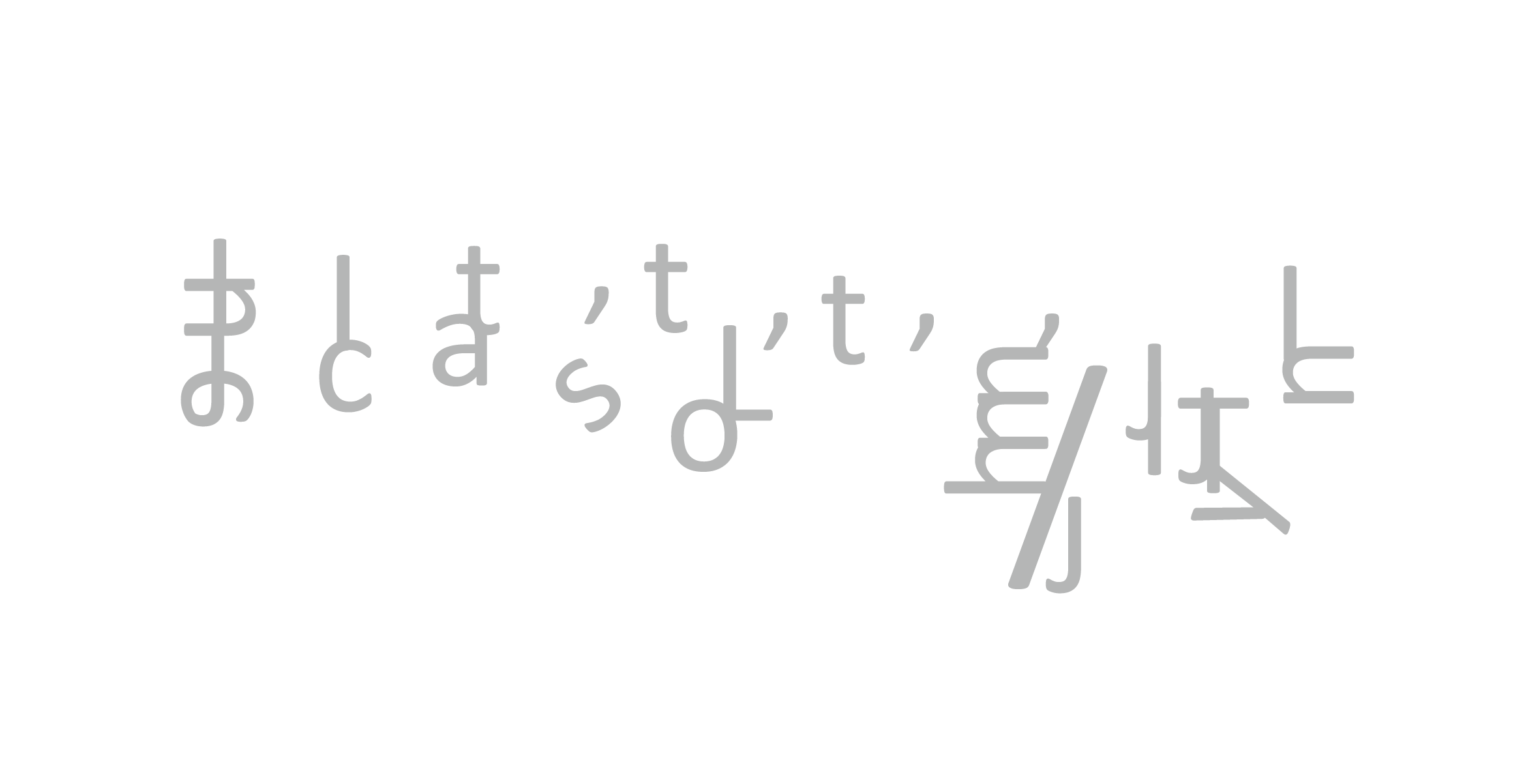これは多分ダンス作品として作られたのだと思う。でも作品の中には福留の魅力的な発話がたくさん含まれていて、中でも作中で福留が「床が好きで、割とこの動きは思い出しちゃう」と言ったのをよく覚えている。肩の力を抜いて言った言葉だったとは思うが、私はこの言葉に作品の主題と力が集約されていると考えた。この文章を読んだ方が、ああわたしも『まとまらない身体と』を観ればよかったと思ってくれた方がいいので、まずは一息に、この作品の面白さは「床が好きで、割とこの動きは思い出しちゃう」に集約される。そして、だから私はこれからその内実を紐解いていく。と銘打っておく。
作品は三場に分かれていて、クリエイションの過程で徐々に増えていった90個くらいの短い振り(2秒で終わるものから、12,3秒ほどのものまでいろいろある)を、無作為にピックアップして20個ほど紹介するという営みに貫かれている。「紹介する」と書いたのは実際に福留が振りを踊ってみせる場合と、その振りのプロフィール、つまり考案者(福留でない場合も多い)や思いついた経緯、繰り返し踊るうちにその振りについて考えたこと等を、文字通り口で喋って紹介する場合の、主に二つの仕方で福留は、私たち観客と「振り」とを出会わせようと試行錯誤するからだ。彼女にとっては知れた仲だが、私たちにとっては初対面の「振り」について、福留は動きと言葉を尽くす。
第一場は16,7分で、20個くらいの振りを福留は実際に踊ってみせる。まず目がいくのは、今まさにやってみせた振りがこの上演が始まってから何個目の振りだったのかを、福留がいちいち数える様子だ。一つの振りを踊っては小さく「15」などと福留は呟き、また次の振りに移っていく。呟かない時もままあるが、それはたまたま声にしなかっただけだろう。20個ほど振りを紹介するとこの一場は唐突に終わる。おそらく福留がカチッと部屋の蛍光灯を点けたのを合図にして、作品は第二場に移っている。二場は22,3分で、この間の福留は私たちとごく自然に語らうような感じだった。「いまやったのは多分24個でした」とか「思い出したのをどんどんやっていこうと思ってやってる」「さっきできたほやほやをやってみよう」「これは〈かつおぶしの動き〉というタイトルがついてます」とか、「(一場のあるシーンを指して)あの時は本気でなんにも考えてなくて」「やってたら楽しくなってきて(長めにやってしまった)」とか、「(もともと)意味がなかった動きなんだけど、やっていくうちにイメージというか動く理由ができてきたりする。それはこういう意味かと思ったとか見てくれた人が言ってきてくれて、"ああそうかも"と思って理由が増えていく」等と話しつつ、時に再現を交えたり、あるいは会場から適宜質問や希望を募り、振りについて解題していく。この“上演らしくない”時間について穿った見方をしてもいいが、そんなことをしたところで意味はないだろうと思うくらい二場の福留は脱力していて、ほとんどへらへら振りの紹介に徹していた。そしてまたこの時間も唐突に区切られ、福留自ら部屋の電気を一部消し、第三場に入っていく。三場は、あえて気を遣って言えば作品中で最も“上演らしい”時間だった。福留は一場や二場と違って終始集中しており、さっきまで共に語らっていた私たちのことなど今は見えていないように見えた。終演後の福留の説明によれば、三場では一場で踊ってみせた20個くらいの振りを、もう一度踊ったということだった。また登場する振りの順番が一場と一致するかどうかは気にせずやっていた、とも言っていた。一観客として観ていた私が把握できる限りにはなるが、事実三場に登場する振りは一場と大きくは変わらなかったので、こう書いていると一場と三場の見え方には大きな違いがなかったと読者は想像するかもしれない。ただ実際に観ているとそこには大きな違いがあった。この違いに焦点を当てるのが本稿の目的である。
一場では、振りと振りの間に概ね「インターバル」が介在していた。それは福留が踊った振りの数を数える時間であり、またその精度について反省する時間であり、そして次に繰り出す振りを思い出し、やるかやらないか決める時間であり、またその振りを空間のどこで実行しようか検討する時間だった。福留は微妙に動いたと思ったら静止したり、口をもごもごやったり身体を実際にちょこっと使ったりして、思うままにインターバルを過ごしていた。不思議なのは、三場においてはこのインターバルが皆無だったことだ。三場は振りという要素に限っていえば一場とほとんど同じ内容であったと言ってもいいのだが、インターバルが消去されることで、あまりに印象が違っていた。終演後の意見会で、この不思議さに関する質問が会場から出た際、福留は以下のように説明した。一場では「動きの始まりと終わりを完結させる」、あるいは「影響し合わないように独立させ」ることに神経を使っていた。一方で三場では「前の流れを受けて、次の動きに移行していく」ように努めており「そうすると結構動ける」、とのことだった。この「結構動ける」というのは、インターバル=中断を締め出せるという意味でほぼ間違いないだろう。
端的に言って、一場が面白かった。見ていて考えることがたくさんあった。一方で三場は面白くなかった。それは福留が比較的無理をしているように感じてしまったからだ。ただ恐らく一般的に舞台作品というのは、概ね福留が第三場を形容して言った「結構動ける」といったようなモードで表現されることが多いだろう。またそれはモードでしかないことをしばしば忘れられ、主題や情動、さらには作品の構成を浸潤していく。そして上演中延々と判断を迫られるプレッシャーから身を守るため、「結構動ける」を最低限満たすべき水準に設定してしまう。これは恐らく重要な生存戦略ではある。延々と判断を迫られる苦痛は、「結構動け」さえすれば無害化できる。苦痛は踊りの相手役に相成り、ダンサーとは言えば苦痛に絡め取られるふりをしてそれを飼いならす。またこういった舞台作品にあって“見もの”なのは、生のままの苦痛が時たま顔を覗かせることだろう。作中、時たま苦痛が賦活化しそれに翻弄されダンサーの身体が痙攣を起こす。これが劇的なものとしてしばしば称揚される。ただ私が本稿で取り上げたいのはこういった苦痛の無害化と賦活化との間の振り幅に関することではない。この作品の主題は、苦痛をいかにコントロールするか/しないかのせめぎ合いから少し距離を置き、苦痛の扱いそれ自体について再考することだったのではないか。苦痛をコントロールの対象とするのではなく、単にそのときの身体と気分が、直面した苦痛を受け入れられるかどうか検討すること。そして検討している間、時間がだらだらと流れていってしまうこと。この事態こそが本作の意義であり、またそこに私は鑑賞者として窮屈でない居場所を見つけた思いがした。
では一場のどのあたりに目をやるべきなのか。先に挙げた「苦痛」とは、舞台作品が往々にして時間に支配されることを発生原因としている。しかし舞台作品はパフォーマーが時間をコントロールし、また同時に時間にパフォーマーがコントロールされることを重要な動力にしており、この制約を単に取り除くというのには恐らく困難が伴う。言い換えれば、時間切れがない振りをしたって単に傲慢に見えるだけという話だ。
一場の福留は、振りについて考えること(思い出す/批評する/精度を出す)ことに神経の大部分を集中させていた。あるいはそういうパフォーマンスをしていた。この様子が、私には苦痛と同居するための取り組み、あるいは時間切れについて都度考え直す(切迫具合を適宜勝手に都合する)姿勢に見えた。
福留が言うところの「動きを独立させる」所作の類縁と思われるが、ひとつの振りを終えた後の福留の態度は、ある種批評的であった。終えた振りの達成度に不満を持っているように見える時もあれば(首を傾げたり、来た道を振り返って見えない動線を手で押して整えたり)、充実した表情で「13」などと呟いて姿勢を正す時もあった。その時間感覚は一定ではなく、急いているように見えるときもあれば、沈黙しきっているあまりこちらを不安にさせることもある。また次の振りに向けて継起する思考は実に取り留めがなく、舞台上に散らばる小道具や美術との距離感を推し測り、次の動線を汲み出そうと思案しているように見えたり、あるいは寝転がるために、床の質感を足の裏で弄っているように見える時もあった。そしてやはりこのあたりの所作も、時間切れについて真摯に考えているようにも、ほとんど気に留めていないようにも見える。
総じて、一場にのみ存在したインターバルとは、都度別の審美眼が前景化し、行為を区切る基準や、空間を認識する視点がすり替わるような場であったのではないか。そしてその眼に抱き合わされるような形で、多様なスケジュールが適宜持ち込まれる。何を良しとするか判断する前提が変わるのだから、当然スケジュールも複数林立し、それが上演において一応継ぎ接ぎされる。とはいえこの見立ては因果を取り違えているかもしれない。多様なスケジュールがまずもって用意され、より気持ちに余裕が生まれるスケジュールにおいて、福留の時間感覚が弛緩し、視座がすり替わると考えることもできるだろう。兎にも角にもこの組み合わせが重要だと感じた。振りの精度の捉え方を変えることと、そこに充填される/それを下支えするスケジュールが複数的であること。この事態にあって、福留は、舞台上において新たな仕方で苦痛と同居していた。
冒頭に記したように、福留は「床が好きで、割とこの動きは思い出しちゃう」と終演後の意見会で言っていた。これは、床に仰向けに寝たまま、肘と膝はあまり曲げずに腕と足を弧状に大きく動かして、腰あたりを中心にずりずり体を回転させるという振りを、自身が今作の上演において比較的頻繁に選び取って踊ってしまうことの説明だった。福留はこの振りが発案された経緯も続けて語った。それは昨年の冬、福留が妊娠3,4ヶ月くらいの折、稽古のためにスタジオイマイチ(山口市)に行った時のことだった。スタジオ入りしてすぐに心身ともに力が抜け、身動きがとれなくなってしまったらしい。福留はただ床に寝転がっているしかできず、時間が無為に過ぎていったという。この経験がこの振りを生み出す端初となったとのことだった。私はこのあたりの話を聞いていて、妊娠・出産を経た福留には「無理をしない」モードが、上演に臨む態度のオプションとしてリストされたのではないか、と考えた。この作品においては、上演とはいえ、それよりも優先すべき体調があるという(生活においては当たり前の)ことが前提にあったのではないか。「床が好き」だったり「割と」「思い出しちゃう」といった自己本位的な気分が住まうだけの空隙を、作品の中に忍び込ませること。気の持ちように沿って、時間切れが何度も設定し直されること。それが一場の姿勢、ひいては三つの場に分けられていた作品の構成から伺い知れるような気がした。
-
村社祐太朗
新聞家主宰。演劇作家。1991年東京生まれ。訥弁の語りを中心にした作品の特異な上演様態は「読むこと」そのものとも言われる。書くことや憶え繰り返すことを疎外せずに実現する上演を模索中。近作に『フードコート』(2019)等。2019-2020年度公益財団法人セゾン文化財団セゾンフェローⅠ。2020-2022年度THEATRE E9 KYOTOアソシエイトアーティスト。2023年2月に新作『とりで』(THEATRE E9 KYOTO)を発表予定。